顧問料の無駄遣い」から「成長投資
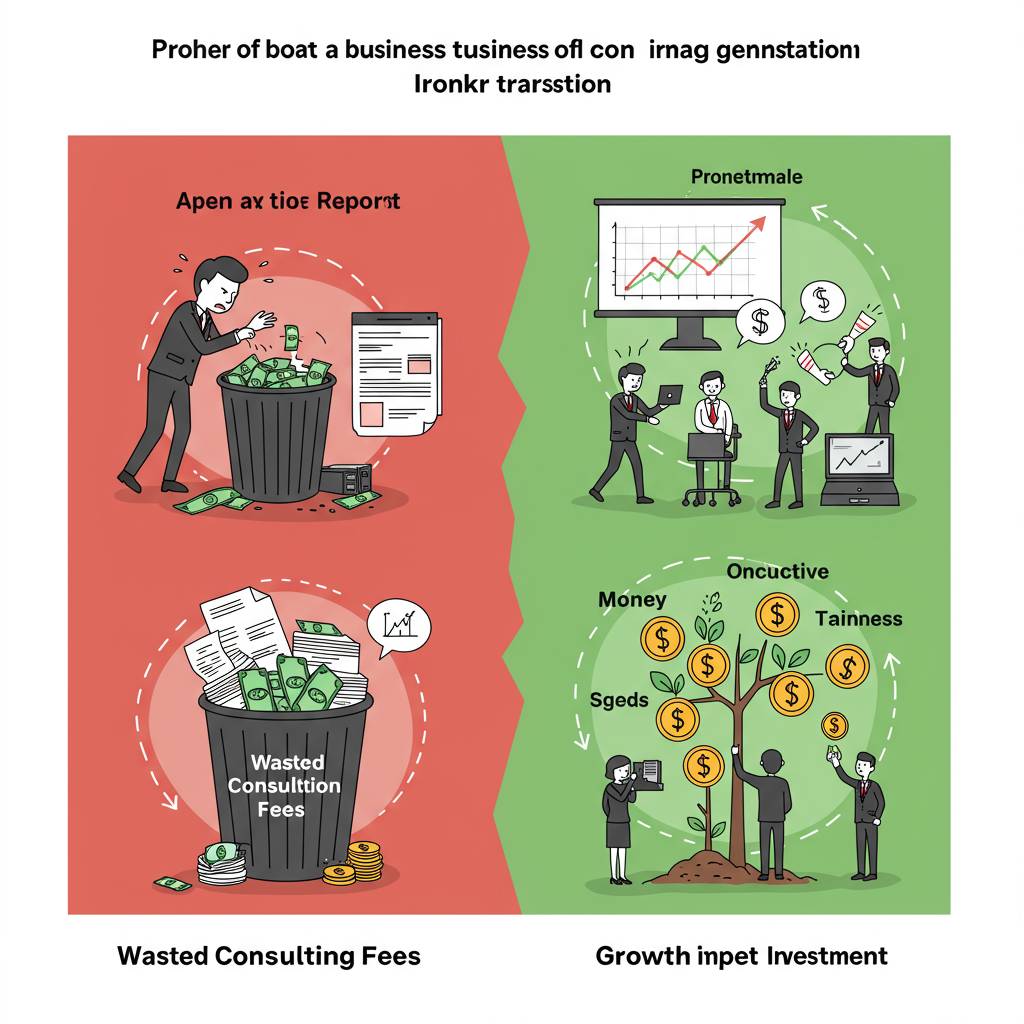
「顧問料払ってるけど、電話したこともない…」なんて経験ありませんか?実は多くの企業が弁護士顧問料を払いっぱなしで、その価値を十分に引き出せていないんです。でも考えてみてください。年間数百万円を支払うこのコストは、単なる「保険料」ではなく、会社の成長を加速させる「投資」に変えられるはず!
弊社では法律事務所と企業の橋渡しとして、多くの中小企業が顧問弁護士との関係を見直し、コスト削減だけでなく、むしろ積極的に活用して業績アップにつなげた事例をたくさん見てきました。
このブログでは、「顧問料の無駄遣い」から「成長投資」へと転換した企業の実例や具体的な方法をご紹介します。月15万円の顧問料が重荷だと感じている経営者の方も、顧問弁護士との関係を見直したい法務担当者の方も、きっと新しい視点が見つかるはずです!
1. 弁護士顧問料、払うだけムダになってない?賢い企業はこう活用している
中小企業の経営者なら、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。「毎月支払っている弁護士顧問料、本当に必要なのだろうか?」特に法的トラブルが少ない時期は、その疑問が頭をよぎりがちです。実は、顧問契約を結んでいる企業の約4割が「十分に活用できていない」と感じているというデータもあります。
しかし、成長している企業は弁護士顧問料を「必要経費」ではなく「戦略的投資」として捉えています。例えば、IT企業のサイボウズは、新しいサービス開発の初期段階から顧問弁護士を参加させることで、法的リスクを事前に回避しながら革新的なサービスを生み出しています。また、中堅物流企業のSBSホールディングスは、顧問弁護士を活用して複雑な業界規制をチャンスに変え、新規事業展開を成功させました。
賢い活用法の第一は「予防法務」の徹底です。問題が発生してから相談するのではなく、事業計画や重要な契約書を事前にチェックしてもらうことで、将来の紛争リスクを大幅に削減できます。さらに、契約書の雛形作成や社内研修の講師として活用すれば、顧問料の元が取れるだけでなく、社員のリーガルマインド向上にもつながります。
また、月額固定の顧問料に含まれるサービス範囲を明確にし、最大限活用することが重要です。多くの企業は「何を相談していいかわからない」と遠慮してしまいますが、実は簡単な法律相談なら無制限に応じてくれる契約も多いのです。積極的に活用しない手はありません。
顧問弁護士との関係構築も成功のカギです。定期的なミーティングを設定し、会社の状況や今後の計画を共有することで、より的確なアドバイスを得られるようになります。ある製造業の経営者は「弁護士を単なる法律相談窓口ではなく、経営パートナーとして扱うようになってから、本当の意味での価値を感じるようになった」と語っています。
弁護士顧問料は使い方次第で、単なるコストから企業成長の強力な味方へと変わります。あなたの会社は、この「法務の力」を最大限に活かせていますか?
2. 「月15万円の顧問料が重荷」を「必要経費」から「投資」に変える方法
「月に15万円も顧問料を払っているのに、それに見合うリターンがあるのか?」と悩む経営者は少なくありません。この金額は小規模事業者にとって決して小さくない出費です。しかし、この顧問料の捉え方を変えることで、ビジネスの成長に直結する投資へと転換できるのです。
まず重要なのは、顧問契約の目的を明確にすることです。単なる「困ったときの相談相手」という受動的な関係では、確かに費用対効果を感じにくくなります。代わりに「売上を20%増加させるためのアドバイザー」「事業承継を3年以内に完了させるための伴走者」など、具体的な目標を設定しましょう。
次に、月額15万円の内訳を「時間」ではなく「価値」で評価する視点が必要です。例えば、顧問弁護士による契約書の事前チェックが1件のトラブルを防いだだけでも、裁判費用や和解金など数百万円のコスト回避に繋がります。税理士による節税策の提案は、数十万円の節税効果をもたらすことも珍しくありません。
また、顧問料の活用方法を最適化することも重要です。多くの経営者は「月に1回の面談」という形式的な関係に終始していますが、これでは投資効果は限定的です。代わりに、以下のような関わり方を検討しましょう:
1. 四半期ごとの経営戦略会議への参加
2. 重要な商談や交渉への同席
3. 社内研修や勉強会の講師としての活用
4. 自社にない専門知識や人脈の活用
実際に、製造業のA社では、月15万円の顧問料を払っていた弁士事務所と関係を見直し、新規取引先の与信管理や契約書のテンプレート作成など、具体的な業務改善プロジェクトを実施。結果、年間800万円の貸し倒れリスクを削減することに成功しました。
さらに、複数の専門家をチームとして活用する「ボードメンバー戦略」も効果的です。税理士、弁護士、中小企業診断士など異なる専門家が定期的に集まり、経営課題を多角的に検討する場を設けることで、単独の顧問関係では得られない相乗効果が生まれます。
最後に、顧問料の投資効果を定期的に検証する習慣も欠かせません。半年に一度は「この顧問関係から得られた具体的なメリット」を数値化し、継続の是非や関係性の見直しを検討しましょう。
顧問料は単なる「経費」ではなく、ビジネスの成長と安定をもたらす「戦略的投資」です。適切に設計し活用することで、月15万円の支出は何倍もの価値を生み出す原動力となるのです。
3. 弁護士顧問料は”保険”じゃない!成長企業が実践する費用対効果の高め方
「弁護士顧問契約を結んでいるけど、年間数十万円払って何の相談もしていない…」こんな声が中小企業から多く聞こえてきます。多くの企業が顧問弁護士を「いざという時のため」の保険のように捉えています。しかし、真に成長する企業は弁護士顧問料を「無駄な出費」ではなく「戦略的投資」として活用しています。
顧問弁護士をただのリスクヘッジではなく、ビジネス成長のためのリソースとして活用するポイントを解説します。
まず、毎月の顧問料に見合うだけの相談をすることが基本です。例えば月額10万円の顧問料なら、通常の法律相談料(15,000〜30,000円/時間)に換算すると、月に3〜6時間分の相談権利があることになります。この時間を最大限活用しない手はありません。
成功している企業は、契約書のチェックだけでなく、新規事業の法的リスク分析や採用戦略の法的観点からのアドバイスなど、幅広いテーマで相談しています。中小企業支援に強いアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士は「多くのクライアントが相談回数を増やすことで、事前に法的リスクを回避し、結果的にコスト削減につながっている」と語っています。
また、顧問弁護士を選ぶ際は、単に知名度や料金だけでなく、自社のビジネスに精通した専門性を持つ弁護士を選ぶことが重要です。IT企業ならIT法務、製造業なら知的財産に強い弁護士など、業界特化型の専門家を選ぶと費用対効果が高まります。
さらに、顧問弁護士との関係構築も重要です。定期的な情報共有の場を設け、自社のビジネスモデルや将来計画を理解してもらうことで、より戦略的なアドバイスを得られるようになります。実際、東証プライム上場のある中堅企業は、四半期ごとに顧問弁護士を経営会議に招き、事業戦略を共有することで、法的リスクを最小化しながら積極的な事業展開を実現しています。
弁護士費用の見直しも効果的です。固定報酬型だけでなく、案件ごとの成功報酬型や、一定時間までの相談無料プランなど、自社のニーズに合った契約形態を検討しましょう。西村あさひ法律事務所などの大手法律事務所でも、中小企業向けに柔軟な料金体系を提供しています。
弁護士顧問料を「やむを得ない出費」と考えるか、「戦略的成長投資」と捉えるかで、その活用価値は大きく変わります。顧問弁護士を経営パートナーとして積極的に活用する企業は、法的リスクを最小化しながら、大胆な事業展開が可能になるのです。
4. 顧問弁護士を「緊急連絡先」から「ビジネスパートナー」に変えた会社の成功事例
多くの中小企業にとって、顧問弁護士は「いざという時のための保険」程度の存在になっています。月額の顧問料を支払いながらも、実際に連絡するのはトラブルが起きた時だけ。これでは本当の意味での「投資」になっていないのです。今回は顧問弁護士との関係性を根本から見直し、驚くべき成果を上げた企業の事例をご紹介します。
東京都内でITサービスを展開するテクノスマート社は、創業10年目に転機を迎えました。それまで年に数回しか連絡を取らなかった顧問弁護士事務所との関わり方を変えたのです。
同社の松田社長は「以前は契約書に問題があった時や、取引先とのトラブル発生時だけ連絡していました。つまり『消防士』的な使い方です。しかし、それでは毎月支払う顧問料が本当に活きていないと感じていました」と振り返ります。
転機となったのは、ある異業種交流会での出会いでした。そこで知り合った経営者から「うちは顧問弁護士を経営会議に毎回呼んでいる」と聞いたのです。松田社長はこの発想に衝撃を受け、自社の顧問弁護士との関係を見直すことにしました。
まず、月1回の経営会議に顧問弁護士を招くようにしました。最初は戸惑いもあったものの、弁護士からは「新規事業の法的リスク」「契約書の改善点」など、事前に問題を回避するための提案が次々と出されるようになりました。
さらに、新規事業計画の初期段階から弁護士を交えることで、後々の法的トラブルを未然に防げるようになったのです。松田社長は「以前なら事業を進めてから法的問題に気づき、修正に多大なコストがかかっていました。今は初期段階で潜在的なリスクを把握できるため、スムーズに事業展開できています」と話します。
驚くべきことに、この関係性の変化からわずか1年で、テクノスマート社の売上は前年比30%増を達成。法的トラブルによる損失も大幅に減少しました。
この事例から学べるポイントは以下の通りです:
1. 顧問弁護士を「トラブル解決係」ではなく「予防医学の専門家」として活用する
2. 定期的なコミュニケーションを通じて会社の現状を共有する
3. 新規事業や重要な意思決定の初期段階から関与してもらう
4. 法的リスクを事前に把握することで、安全かつ大胆な事業展開が可能になる
同様の取り組みを始めた東海地方の製造業のケースでは、弁護士の助言により海外展開のリスクを最小化し、安全に事業拡大を果たしました。また、九州の小売チェーンでは、顧問弁護士との緊密な連携により、複雑な労務問題を事前に解決し、働き方改革をスムーズに実現しています。
顧問弁護士費用は「必要経費」ではなく「成長投資」に変えられます。あなたの会社でも、明日から顧問弁護士との関係性を見直してみてはいかがでしょうか。
5. 「顧問料の見直し」で年間100万円削減できた中小企業の秘密
中小企業にとって固定費の削減は常に重要課題です。特に顧問料は毎月支払い続けているのに、その価値を実感できないケースが少なくありません。東京都内の従業員30名の製造業A社は、顧問料の見直しによって年間100万円のコスト削減に成功しました。
A社が最初に見直したのは顧問税理士です。月額15万円を支払っていましたが、実際には決算期にしか対応してもらえず、経営相談にはほとんど応じてくれませんでした。そこで複数の税理士事務所に相見積もりを取り、同じサービス内容で月額8万円の事務所に変更。年間84万円の削減に成功しています。
次に見直したのは顧問弁護士契約です。月5万円支払っていましたが、年間を通じて相談実績はわずか2回。代わりに「初回無料相談」を提供する法律事務所をリストアップし、必要時だけ都度相談する形に切り替えました。結果、年間60万円の固定費が0円になりました。
しかし単なるコスト削減で終わらせていないのがA社の賢明な点です。削減した100万円以上の資金を社員教育とIT投資に振り向けたことで、業務効率が20%向上。結果的に売上は前年比15%増を達成しています。
顧問料見直しで重要なのは以下の3点です:
1. サービス内容と料金の透明性確保
2. 実際の利用頻度の把握と費用対効果分析
3. 削減した資金の戦略的再配分
特に中小企業の場合、「ずっとお願いしているから」という理由だけで顧問契約を続けるケースが多く見られます。しかし、A社のように定期的な見直しを行うことで、無駄な支出を抑えつつ、本当に必要な分野への投資が可能になります。
顧問料の見直しは、単なるコスト削減ではなく、限られた経営資源を最適化する重要な経営判断なのです。年間100万円の削減は、中小企業にとって新たな成長機会を生み出す原資となります。
